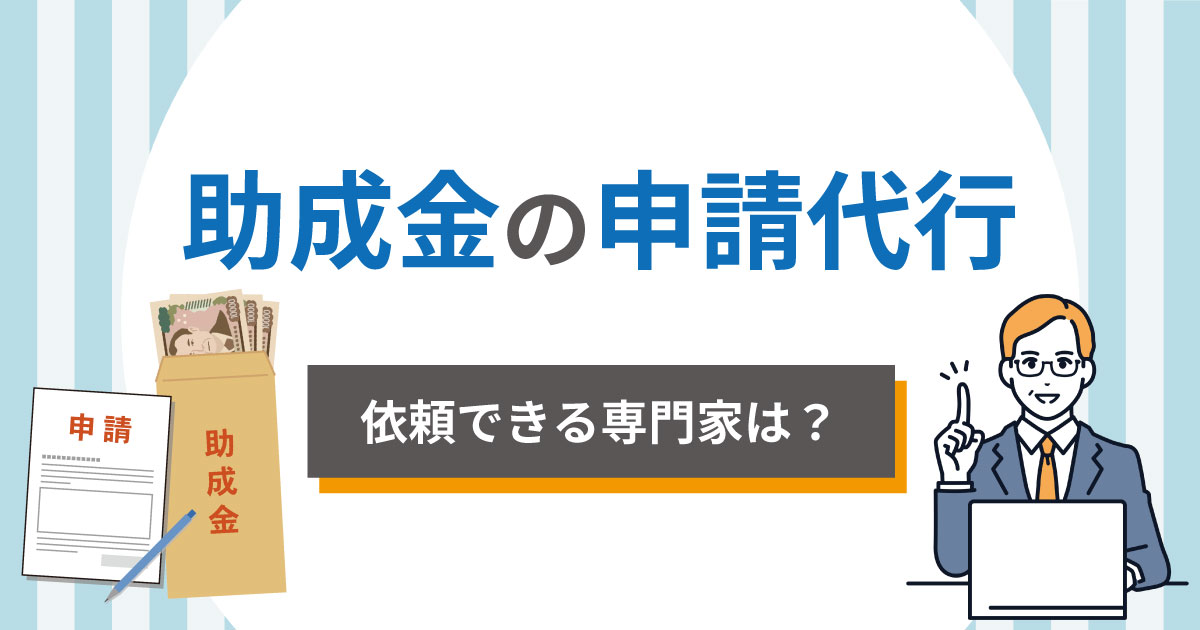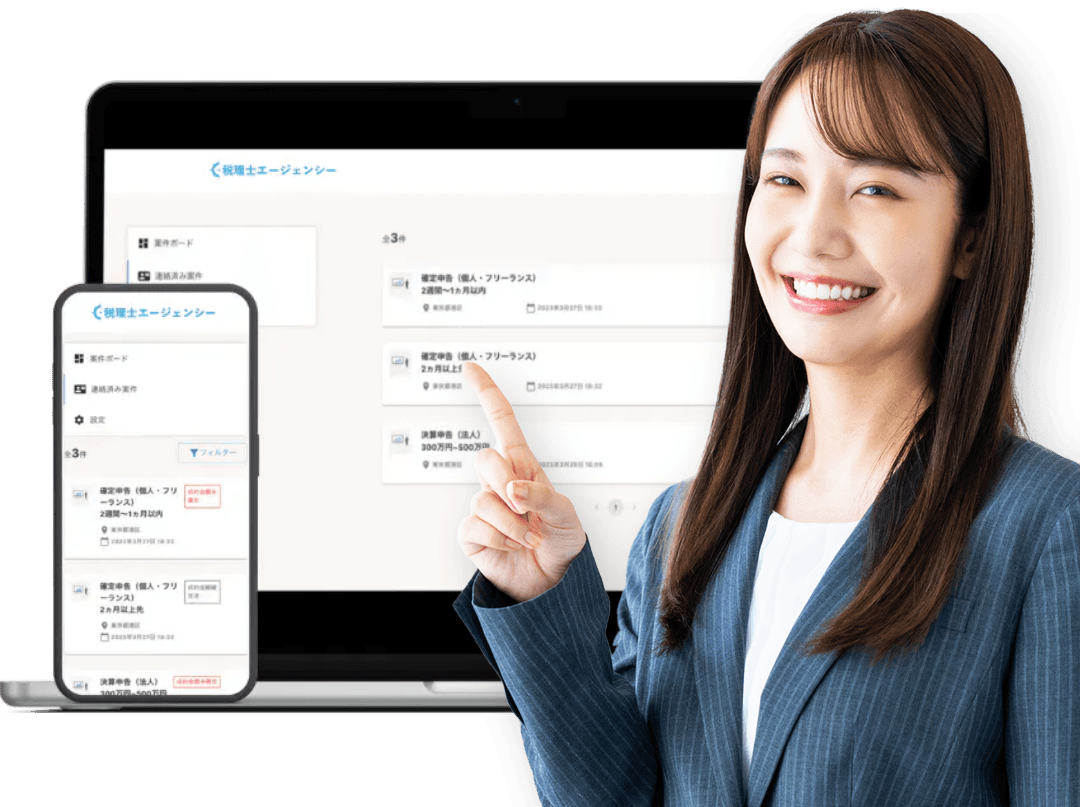助成金とは、人材育成や雇用環境の改善に取り組む法人や個人事業主を支援するために、国や地方公共団体から支給されるお金のことで、助成金は資金繰りに悩む中小企業にとって非常にありがたい制度です。
しかし、申請の際には複雑な書類を作成して提出する必要があり、時間と労力がかかることから、専門家による申請代行がよく活用されています。
この記事では、助成金の申請代行を依頼できる専門家や、申請代行のメリット・デメリット、2023年に利用できる主な助成金一覧について解説しますのでぜひお役立て下さい。
助成金の申請代行は社会保険労務士のみ可能

助成金の申請代行は社会保険労務士(社労士)の独占業務とされており、社労士以外の者が事業者に代わって申請することは禁止されています。
これに違反すると社会保険労務士法に基づき、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
なお、禁止されているのは補助金の申請代行で、事業者が自ら申請することは何ら問題ありません。
助成金と混同されやすいものに補助金があり、助成金と補助金は国や地方公共団体から支給されるお金である点では共通していますが、所管や目的が異なります。
補助金は経済産業省や地方自治体の所管で、国や地域の政策目標の実現を目的としているのに対し、助成金は厚生労働省の所管で、人材育成や雇用環境の改善の取り組みへの支援を目的としています。
また、助成金は要件を満たしていれば基本的に支給されるのに対して、補助金は審査があり、誰でも支給されるわけではありません。
もっとも、「助成金」という名称が付けられているのに補助金としての性質が強いものもあり、助成金と補助金は明確に区別されているわけではありません。
特にインターネット上では補助金と助成金を混同している情報も多いため注意が必要です。
当記事では、厚生労働省が所管するものを助成金と称します。
助成金の申請代行にかかる費用相場

助成金の申請代行を依頼したときに社労士に支払う費用は、申請の際に必要な手数料と、支給が認められた際に支給された金額に応じて支払われる成果報酬に分けられるのが一般的です。
手数料(又は着手金)の額は社労士事務所によって異なりますが、相場は2万円から10万円程度です。
| 手数料相場 | 2万円~10万円程度 |
|---|---|
| 成果報酬相場 | 支給金額の10%程度 |
顧問契約を締結している場合には手数料を割引したり、無料(完全成果報酬制)としている社労士事務所もあります。
成果報酬の額も社労士事務所によって異なりますが、助成金の支給金額の10%程度とされることが一般的です。
助成金の申請代行を依頼するメリット

助成金の申請代行を依頼するメリットは次の通りです。
- ニーズに応じた助成金を提案してくれる
- 複雑な書類作成をサポートしてくれる
- 事業計画の策定や改善のアドバイスを貰える
- 申請成功率が高まる可能性が大きい
助成金は会社が自ら申請することも可能ですが、社労士に依頼するとさまざまなメリットがあります。
ニーズに応じた助成金を提案してくれる
一つは、会社のニーズに合った適切な助成金を申請してもらえる点です。
助成金の種類は多岐にわたり、この記事でご紹介した助成金はほんの一部に過ぎません。
そして、支給の要件や必要書類は助成金の種類によって異なります。
自社に合う助成金は何か、どのような要件で支給されるのか、申請の際に必要な書類は何か、といった情報を自社で調査するのは手間がかかります。
「せっかく自社のニーズに合う助成金があったのに、気づかず申請ができなかった」ということになれば非常にもったいない話です。 社労士は助成金に関する法律や制度に関する専門家で、各種助成金の種類や支給に必要な要件・手続を把握していますので、自社の取り組みに合う助成金を提案してもらうことができます。
複雑な書類作成をサポートしてくれる

助成金を申請するためには、所定の期限までに必要な書類を作成して提出しなければなりません。
助成金を申請するための書類は複雑で量も多いため、作成にかなりの時間と手間を必要としますし、初めての助成金を申請する際にはミスも生じやすくなります。
「何度か申請したことがある助成金なら簡単だろう」と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
なぜなら、助成金の要件や労働法の規制は毎年のように改正が行われますので、前回の申請時と同じように申請すれば通るわけではないからです。
費用を節約するために自分で書類を用意すると、準備に時間がかかるだけでなく、申請後に何度も書類の不備を指摘され、結局不支給になるという事態も起こり得ます。
社労士は法律や制度の改正に精通しており、助成金申請に関する知識や経験に基づいて申請書類を作成してくれます。
社労士に依頼することで書類の作成にかかる時間を短縮することができ、ミスも防ぐことができるのです。
事業計画の策定や改善のアドバイスを貰える

助成金の申請の際には「計画書」の作成が必要となる場合があります。
たとえばキャリアアップ助成金の申請の際には計画期間中に講じる措置や目標を記載した「キャリアアップ計画書」を、人材確保等支援助成金(テレワークコース)の申請の際には支給対象となる経費の見込額や就業規則等の整備予定を記載した「テレワーク実施計画書」を作成し、申請書と併せて提出する必要があります。
このような書類は助成金申請のために必要なだけでなく、会社がこれから取り組む施策を明確にする意味でも重要であり、計画書を作成する過程で会社の課題や人事戦略の方向性が定まるという副産物も期待できます。
社労士に助成金申請を依頼することで、計画書の策定や改善を通じて会社の人事戦略について第三者的な立場でアドバイスをもらうことができます。
申請成功率が高まる可能性が大きい
助成金は補助金と異なり、要件を満たしていれば基本的に受給することができます。
しかし、そもそも支給要件を満たしているか判断することが難しかったり、支給要件を満たしていても申請書の記載が不十分で申請が通らないことがあります。
社労士は人事労務の専門化ですので、自社が助成金申請に必要な要件を満たしているか正確に把握し、それを申請書類に的確に反映させることができます。
これにより、自社で申請するときと比べて助成金申請が通る可能性が高まります。
助成金の申請代行を依頼するデメリット

助成金の申請代行を依頼するデメリットは次の通りです。
- 手数料や成果報酬を払う必要がある
- 申請代行を依頼する業者選びが難しい
助成金申請を社労士に依頼することにはデメリットもあるので、しっかり抑えておきましょう。
手数料や成果報酬を払う必要がある

まずは手数料や成果報酬などの費用を支払う必要がある点です。
特に手数料は申請が通らなかったときでも返金されないので、万が一助成金の支給を受けられなかったときには余計な出費となってしまいます。
そのような事態を避けるためには、手数料がなるべく安い社労士や、完全成果報酬制で依頼を受けてくれる社労士事務所を探すとよいでしょう。
ただし、そのような社労士事務所は申請が通った場合の成果報酬を高めに設定していることが多いので注意が必要です。
申請代行を依頼する業者選びが難しい
助成金申請を代行できるのは社労士だけですが、「社労士なら誰に依頼しても変わらない」というわけではありません。
助成金の申請を成功させる確率を少しでも上げるためには、助成金申請の知識と経験が豊富な社労士に依頼するのが重要なのは言うまでもありません。
しかし、社労士の中には助成金申請の経験が浅い人もいますし、助成金申請代行を積極的に受けない、あるいは既存の顧問先からの依頼しか受けていない社労士も多くいます。
申請代行の費用も社労士によって異なります。
手数料と成果報酬が両方かかる場合もありますし、手数料を無料にして成果報酬を高めに設定している社労士もいますので、費用の比較は簡単ではありません。
できるだけ費用が安く、助成金に関する知識と経験が豊富な社労士に依頼するのがベストですが、業者を探すのは骨の折れる作業です。
これも申請代行を依頼するデメリットの一つと言えるでしょう。
助成金の申請代行に関するよくある質問
助成金は必ずもらえるのですか?
助成金は要件を満たしていれば基本的に支給されますが、100%もらえるわけではありません。
要件を満たしているか微妙なケースがあったり、申請書類に不備があって不支給とされるケースもあるからです。
また、助成金の種類によって申請が通りやすいものと通りにくいものがあったり、同じ助成金でも年度によって通りやすさが違うことがあります。
助成金申請を成功させる確率を少し上げるためには、助成金の要件をしっかり理解すること、そして経験豊富な社労士に依頼することが重要なポイントとなります。
また、助成金の原資は事業主が支払う雇用保険料ですので、労働保険料を納付している事業主でなければ申請できません。
また、助成金を申請すると、労働基準法を始めとする労働法規を遵守していることや、就業規則などの規程類が整っていることがチェックされ、コンプライアンス体制に問題があると助成金が通らないことがあります。
日頃から労務のコンプライアンスを遵守するための取り組みをしていることが重要です。
助成金は返済しなくてもよいのですか?
助成金は融資と異なり、支給を受けたお金を後から返済する必要はありません。
そのため、資金繰りに悩む経営者にとっては大変魅力的な制度だと言えます。
ただし、不正受給した助成金は返還を求められることがあります。
不正受給とは、支給要件を満たしていないにもかかわらず申請書類に虚偽の情報を記載することで助成金の申請を受けようとする行為です。
新型コロナウイルスの影響で雇用調整助成金の要件が緩和されましたが、それに乗じて不正受給をしたケースが多く発覚し、社会問題化したのは皆さんの記憶に新しいところでしょう。
不正受給が発覚すると、支給を受けた助成金の返還を求められるだけでなく、労働局により不正の事実が公表されたり、刑事事件に発展することもあります。
助成金は何度でも申請できますか?
助成金は要件さえ満たしていれば何度でも申請することができます。
ただし、助成金には申請期限が決められているものも多く、申請期限を徒過してしまうと申請はできません。
助成金は課税の対象になりますか?
あまり知られていませんが、助成金は基本的に課税対象となり、雑収入として計上されます。
助成金の申請代行を行政書士や税理士に依頼するのは違法?
助成金の申請を代行できるのは社労士だけで、行政書士や税理士に依頼することはできません。
社労士資格がないにもかかわらず「助成金コンサルタント」などと称して助成金の申請を進めてくる業者は少なくありませんが、このような業者が申請を代行すれば違法となります。違法な業者に申請を依頼した場合、会社も違法行為の片棒を担ぐことになりますので十分に注意が必要です。
他方、助成金でなく補助金であれば行政書士、税理士、中小企業診断士など他の専門化でも申請代行が可能です。
もちろん、社労士も助成金申請を代行することができます。
申込者は個人事業主でも助成金の申請はできますか?
助成金を申請することができるのは会社をはじめとする事業者ですが、個人事業主も事業者であることには変わりありませんので、要件さえ満たしていれば助成金の申請は可能です。
しかし、助成金は雇用保険料を原資としていますので、従業員を雇っていなかったり、雇用保険に加入していない場合には対象となりません。
また、助成金によっては従業員数の要件があったり、従業員数によって給付率が異なることがありますので注意しましょう。
2023年に利用できる主な助成金一覧
ここでは令和5年度に利用できる主な助成金は次の通りです。
- キャリアアップ助成金
- 人材確保等支援助成金
- 働き方改革推進支援助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
- 両立支援助成金
それぞれの助成金について詳しく解説していきます。
キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、有期雇用社員、パート社員、派遣社員といったいわゆる非正規雇用の労働者を正社員にしたり(正社員化支援)、処遇改善の取り組みを実施した(処遇改善支援)事業主に対して支給される助成金です。
正社員化支援には、契約社員など有期雇用の労働者を正社員として雇用したときに支給される「正社員化コース」と、障害を持つ人を正社員として雇用したときに支給される「障害者正社員化コース」の2種類があります。
処遇改善支援には、賃金規定を改定するなどして有期雇用労働者等の基本給を3%以上増額したときに支給される「賃金規定等改定コース」、有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用したときに支給される「賃金規定等共通化コース」、有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入・支給したり、積立てを実施したときに支給される「賞与・退職金制度導入コース」。有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用したときに支給される「短時間労働者労働時間延長コース」の4種類があります。
働き方改革の流れの中で、正規雇用の労働者と非正規雇用の労働者の待遇の間で合理的な理由のない格差をなくすことを主眼とした「同一労働同一賃金」の考え方が浸透しつつあり、賃金規定等改定コースや賃金規定等共通化コースは同一労働同一賃金に取り組む企業で広く活用されています。
人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上を図るなどして、人材の確保・定着に努めた事業主に支給される助成金です。
令和5年度はいくつかのコースを利用することができますが、代表的なものに「外国人労働者就労環境整備助成コース」と「テレワークコース」があります。
外国人労働者就労環境整備助成コースは外国人を雇用する事業場で、就業規則等の社内規程を多言語化するなど外国人が働きやすい職場環境の整備を行った事業者に対し、通訳費・翻訳料などかかった費用の2分の1から3分の2が支給されるものです。
テレワークコースは、良質なテレワークを制度として導入・実施した事業者に対し、規程の作成・変更やテレワーク用の通信機器等の導入・運用にかかった費用の一部を支給するものです。 特にテレワークコースは、新型コロナウイルスの感染拡大後の在宅勤務の普及により注目されています。
働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援助成金は、労働時間の短縮や勤務間インターバルの導入など、働き方改革の推進に取り組む事業者を対象とした助成金です。
令和5年度は、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース、団体推進コース、適用猶予業種等対応コースの5種類を申請することができます。
このうち「適用猶予業種等対応コース」は、働き方改革の猶予措置が適用されている建築業、運送業、病院などを対象としたコースで、勤怠管理システムなどを導入したときに費用の4分の3から5分の4が支給されるものです。
システム導入の際に利用できる補助金としてIT導入補助金がありますが、IT導入補助金の通常枠の補助率が2分の1であるのに対して、適用猶予業種等対応コースは補助率が高いのが魅力です。
特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、就職が困難な事情のある人を公共職業安定所(ハローワーク)の紹介で雇用した場合に支給される助成金です。
略して「特開金(とっかいきん)」と呼ばれることもあり、最もよく利用されるのは「特定就職困難者コース」です。
これは障害のある人や60歳以上の高年齢者を雇用した事業者が対象となる制度で、期間に応じて60万円から240万円が分割で支給されます(短時間労働者でなく、中小企業事業主の場合)。
両立支援助成金

両立支援助成金は、家庭と仕事の両立に取り組む事業主を支給対象とする助成金で、令和5年度は出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コースの3種類を利用することができます。
出生時両立支援コースは「子育てパパ支援助成金」とも呼ばれ、男性が育休を取りやすい環境づくりに取り組み、子の出生から8週間以内に5日以上の育休を取得した男性労働者が出た場合に最低20万円が支給されるものです。
男性の育休取得に対する関心が高まっているのに伴って大きな注目を集めています助成金です。 介護離職防止支援コースは介護休業を取得する労働者が、育児休業等支援コースは育児休業を取得する労働者が出たときに支給対象となります。